こんにちは!かいりおです!
いきなりですが、「自己肯定感」という言葉を聞くと、どんなイメージが思い浮かびますか?
「自信がある人」「ポジティブな人」「明るくて前向きな人」など、そんな印象を持つ人も多いと思います。 でも、山根洋士さんの『「自己肯定感低めの人」のための本』を読んで、そのイメージが大きく変わりました。
この本が教えてくれたのは、自己肯定感は“感覚”であり、点数で測れるようなものではないということ。 「このままの自分でいいんだ」と思える感覚があれば、それが自己肯定感だというのです。
僕自身、小中高と野球部に所属していて、現在も草野球を続けています。 ピッチャーやショートを任されることもある中で、ミスを引きずって自分を責めてしまうことが多かった僕にとって、この考え方はすごく新鮮でした。
今回は、この本から得た14の気づきを2回に分けてご紹介しながら、僕自身の経験や感じたことも交えて、感想文としてまとめていきたいと思います。
自己肯定感とは「感覚」である
自信があるとか、ポジティブ思考だとかは関係なく、「このままの自分でいい」と感じられる感覚こそが、自己肯定感です。僕はこれを読んで、野球でエラーした時のことを思い出しました。「あー、またやっちゃった」と落ち込むけど、それでもグラウンドに立ち続ける自分がいる。その姿勢こそが、自己肯定感だったのかもしれません。
数値で測れるものではない
自己肯定感は「高い・低い」で表すよりも、「ある・ない」という感覚に近いもの。50点、70点といったものではありません。僕も自分を点数で評価していた時期がありました。でも、数字で自己評価をしても、結局納得できなかったんですよね。
高めようとしなくていい
「自己肯定感を高めよう」とすることが、逆に「今の自分は不十分」という思い込みを強めてしまうこともあります。だから、「高めよう」と焦る必要はないんですね。
悩んでいる自分を否定しない
問題や悩みに直面したとき、「それが今の自分なんだ」と受け入れる姿勢が、自己肯定感につながります。僕も仕事を3日で辞めたとき、「なんて根性ないんだ」と自己嫌悪しました。でも、あのときの決断がなかったら、今の仕事にも出会えていない。そう思えるようになってから、気持ちが少し楽になりました。
人の行動の9割は無意識
僕たちの普段の行動のほとんどは、無意識によるもの。だからこそ、自分のことを自分で理解していないことが多いのです。委託ドライバーの仕事でも、道順や荷物の積み方が自然と習慣になっていて、「なぜそうするのか」は意識してないことが多いです。
「今年こそ○○」が叶わないのは、心のブレーキのせい
「今年こそダイエット」「今年こそ早起き」といった目標が達成できないのは、意志が弱いからではなく、無意識に働く“メンタルノイズ”という心のクセが原因です。
メンタルノイズ=無意識の思い込み
自己否定ではなく、「ただの思い込み」「心のクセ」として捉えると、少し楽になります。僕は「社会人は1つの職場で長く続けなきゃダメ」と思い込んでいましたが、それが重荷になっていたんです。今では、「働き方はいろいろある」と考えられるようになりました。
これらの前半7つの気づきは、「無理に変わろうとしない」ことの大切さを教えてくれます。
「今の自分がそのままでOK」と思えることが、変化の一歩につながるんだなと感じました。
後編では、残りの7つの気づきを通して、「実際にどう行動に移していくか」に焦点を当てていきます。
「何かを始めたい」「でも踏み出せない」と思っている人にとって、ヒントになるはずです。
今回はこんな感じで終わろうと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️
でたまた!

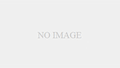

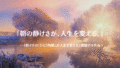

コメント