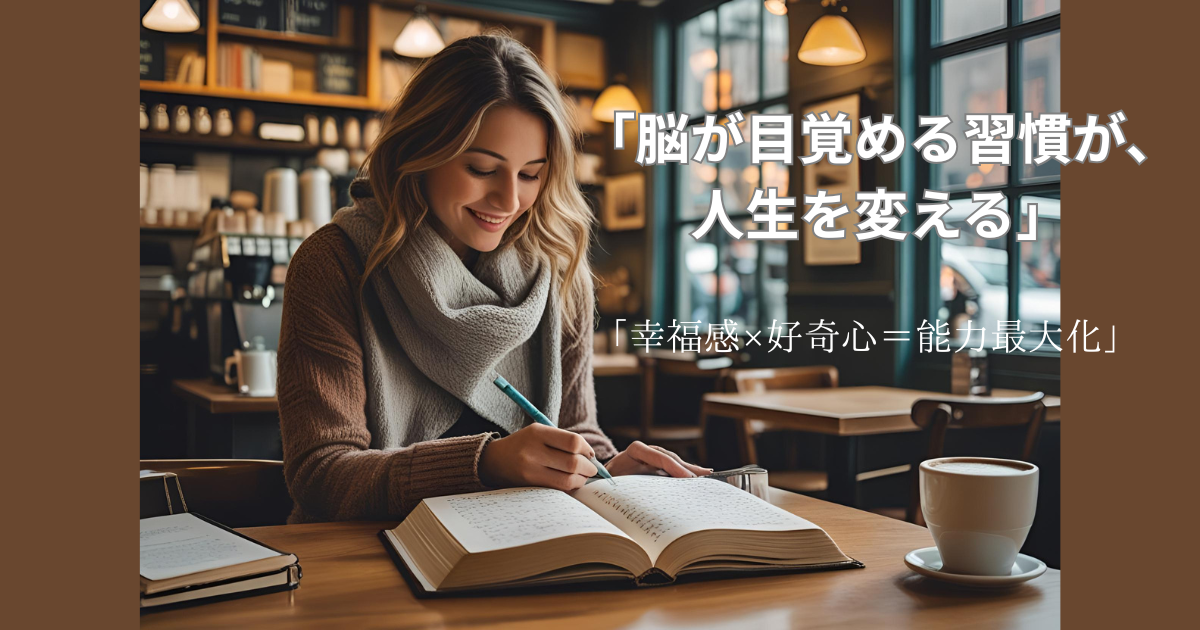
こんにちは!かいりおです 🌱
今回は、瀧靖之さんの脳が目覚めるたった1つの習慣を読んだ僕の感想を皆さんに共有させていただきたいと思います!
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
最近、僕は毎朝のルーティンとして、アファメーション・瞑想・ジャーナリング・読書・ブログ記事作成を行っています。
誰に言われたわけでもなく、自分で選んで取り入れた習慣です。
実を言えば、これを始める前までは「やらなきゃいけないこと」を中心に日々を過ごしていました。
でも、この本――『脳が目覚めるたった1つの習慣』(瀧靖之 著)を読んで、「自分にとって心地いいことや楽しいことを選ぶ」という行動こそが、脳を活性化させる鍵だと知ったとき、自分の過去の選択の数々が浮かび上がってきました。
脳を目覚めさせるのは「幸せになろうとする行動」
この本で特に印象に残ったのは、「幸せのために行動すると、クリエイティビティが300%アップする」という部分です。
僕はこれまで、「成果を出すためには我慢が必要だ」と思い込んでいました。小学生の頃からずっと野球に打ち込み、高校では硬式野球部で毎日のように泥だらけになって練習していました。
でも正直、心から「楽しい」と思えていたわけではない時期もありました。ただ「レギュラーになるにはやらなきゃ」「試合に出るには必要だ」と思って無理やり自分を奮い立たせていた感覚です。
けれど今振り返ると、たまにピッチャーを任されたとき、いつもよりワクワクしていた気がします。
あのときは「任された!」という喜びや「投げて抑えてやるぞ!」という自分発の意欲がありました。その感情が、自分の集中力やパフォーマンスを自然と高めていたんだと思います。
著者は「成果を出した人が幸せになるのではなく、幸せな人が成果を出す」と言っていますが、それはまさに僕が無意識に感じていたことと重なりました。
つまり、楽しくて主体的な状態のときこそ、本来の能力が発揮されるのです。
「この道しかない」は危険。心に余裕を持つことがカギ
本の中で「この道しかないと思い詰めると、心に余裕が持てなくなる」という一節がありました。これはまさに僕自身の社会人としての最初の一歩に当てはまります。
建築設計科を卒業し、施工管理の会社に就職しました。
でも、たったの3日で辞めました。いま振り返ると「根性なし」と言われても仕方ない選択かもしれません。
ただ、僕はそのとき、現場で感じた「これは違う」という違和感を無視できませんでした。
もし「この会社で頑張らなければ人生終わる」と思い込んでいたら、間違いなく心が折れていたと思います。
その後、日本郵便の委託、左川急便、そして今のヤマト運輸の委託と、働く環境を変えながら自分に合ったスタイルを模索してきました。
一つの仕事に固執しすぎなかったからこそ、今こうして朝活ルーティンを楽しんだり、ブログに向き合う余裕も生まれたのだと思います。
「幸福度が高い人」の周囲にいると、自分も変わる
「主観的幸福度が高い人の近くにいると、それがうつる」と本にありましたが、これも実感しています。
正直に言えば、副業としてLINEスタンプやInstagramを始めたとき、誰にも相談せず孤独にやっていたことで、途中で投げ出してしまいました。
でも最近は、習慣の共有ができる仲間や、似たような悩みを持つ人たちとつながることで「一人じゃない」という安心感とモチベーションを持てるようになりました。
これは脳科学的にも正しいことで、ポジティブな人の近くにいると、自分の脳も活性化しやすい状態になるのだと学びました。
つまり、「人間関係を選ぶこと」もまた、自分の脳の状態を整える重要な選択肢なんですね。
小さな「楽しい」を積み重ねる生活へ
最近では、休日には好きなYouTubeを見たり、草野球をしたり、読書で知らない世界に触れたり、ブログを書くことで自分の考えを形にしたりと、小さな「楽しい」を大切にしています。
また、音楽にはドーパミンを分泌させて脳を報酬モードにする効果があるということも知り、朝のルーティン中にも取り入れるようになりました。
それらの積み重ねによって、「成果を出すための努力」が「自分のための楽しい努力」へと変わってきた気がします。
「嫌だ」「やらなければ」に支配されていた自分
僕はこれまで、何かに挑戦しようとするたびに「〜しなければならない」と考えすぎて、かえって自分を縛ってしまうクセがありました。
副業として始めたLINEスタンプ制作やInstagramの運用も、「やるからには結果を出さなきゃ」「続けなければ意味がない」と無意識にプレッシャーをかけてしまっていたんです。
そうなると、最初にあった好奇心やワクワク感が薄れていき、「やらなきゃいけないからやる」という義務感に変わり、最終的には手が止まってしまいました。
これはまさに、脳の能力スイッチがオフになっていた状態だったのだと、この本を読んで気づかされました。
本書には、「嫌だ」「興味がない」「〜しなければならない」という思考は、脳の能力スイッチを切ってしまうとありました。
納得です。だからこそ、これからは「やりたいからやる」「楽しそうだからやってみる」といった、自分の好奇心を軸に行動していきたいと強く感じました。
「〜すべき」から「〜したい」への転換。
これは、義務感に押しつぶされがちな現代人にとって非常に重要な考え方だと思います。
特に「挑戦したいけど一歩踏み出せない」と感じている方には、「まずは心が動く方向に進んでいい」という許可を自分に出すことを、ぜひ意識してほしいです。
ひとつの道に縛られない勇気が、自分を自由にする
僕のこれまでの経歴は決して一直線ではありません。施工管理会社に就職するも3日で退職し、郵便や運送の委託業務を経て今に至ります。
学生時代のバイトも、コンビニ、Uber eats、引越し、野菜キットの仕分けなど多岐にわたりました。
一見、まとまりのない経歴に見えるかもしれません。
でも、今振り返ると、いろんな仕事や環境を経験したことで得られた学びや出会いは、自分にとって大きな財産になっていると感じます。
本書では、「この道しかない」と思い込むと心の余裕がなくなり、挫折しやすくなると書かれていました。
まさにその通りだと思います。
今の仕事が合わなければ、別の仕事をすればいい。
何度でもやり直せる。
そんな心の柔軟さがあるからこそ、本来の力を発揮できるのだと、僕自身の経験からも実感しています。
特に若い世代や、今まさに転職やキャリアチェンジを考えている方に伝えたいのは、「いま選んでいる道がすべてじゃない」ということ。
複数の選択肢があることを知るだけでも、心はぐっと軽くなります。
僕たちは、何かに失敗したとき、それを「人生の終わり」と感じてしまいがちです。
でも、実際にはそこから別の道が始まることもある。
だからこそ、一つの道にこだわらず、自分の心の声を大切にしていきたいですね。
読者のあなたへ:行動のきっかけは“気持ちよさ”でいい
もしあなたが今、何かに挑戦したいと思っているけど一歩踏み出せないでいるなら、まず「自分が気持ちいいと感じること」に目を向けてみてください。
頑張る前に、ちょっとワクワクすること、楽しいと思えることをしてみてください。
それは小さなことで構いません。
コンビニの新作スイーツでもいいし、朝ちょっとだけ早起きして好きな音楽を聴くだけでもいい。
自分にとって心地いいことを「選んで」行動することが、実は脳を目覚めさせ、能力を最大限に引き出す一歩になるのです。
最後に
この本は、脳科学の観点から「幸せに生きること=脳の性能を最大限に活かすこと」だと教えてくれます。
もし、今の生活に少しでも閉塞感を感じているなら、それは自分の脳が「もっと楽しく行こうよ」とサインを出しているのかもしれません。
『脳が目覚めるたった1つの習慣』は、そんなサインに気づき、幸せへの選択肢を増やしてくれる一冊です。
無理せず、自分らしく、でも前に進みたい――そんなあなたにこそ、読んでほしい本です。
今回はここまで!
また次回のかいりおblogでお会いしましょう!
ではまた 🌱
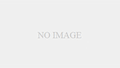



コメント