こんにちは!かいりおです!
今回読んだのは、加藤俊徳さんの『一生頭が良くなり続ける もっとすごい脳の使い方』という本です。
はじめに 〜「自分の頭はもっと使える」と思えた一冊〜
この本を通して、脳の使い方ひとつで、自分の行動も、未来も変えられると感じました。この記事では、本の中で印象的だった学びや、僕自身の経験を交えた気づき、そしてこれを読んでくれているあなたへの「行動のヒント」をお伝えします。
「やり抜く力」がある人ほど、知識を応用できる
この本の冒頭で書かれていたのが、「やり抜く力」がある人は、新しいことを吸収し、それを応用できるということ。
僕はこれを読んで、過去に挑戦して挫折したLINEスタンプ制作やインスタ運用を思い出しました。正直、途中で飽きてやめてしまったんです。でも、それって「やり抜く力」が足りなかったということ。
「小さな成功体験」から自信を育て、脳をいい方向に鍛えることができるんだと感じています。
感覚で動くだけじゃ、実行力は育たない
著者は「実行力が弱い人は、感覚で突っ走る傾向がある」と書いています。
これ、まさに昔の僕です。施工管理の会社に入って3日で辞めたのも、「なんか違うな」と感覚的に判断した結果でした。あの時、もう少し論理的に「自分が何を求めていて、何が向いていないのか」を分析できていたら、もっと良い選択ができていたかもしれません。
左脳=論理的思考や計画を担当する脳番地を育てることが、社会で「考えて動く力」につながるのだと痛感しました。
五感の入力を減らせば、集中力が上がる
「集中したいなら、音や匂い、視覚情報を減らすべき」とのアドバイスもとても実践的でした。
僕は配達の合間、いつも車の中で休憩をとっています。今まではスマホでYouTubeばっか見いましたが、最近は、読書や、ブログを書くようにしています。
脳をリセットする時間を意識的に作ることで、次の配達も集中して取り組めるようになりました。
本気の会話が、記憶に残る「ファイアリング」になる
著者は、「誠意ある会話」は記憶の定着を助けると言っています。
これを実感したのは、お客様とのやり取りの中です。ある日、再配達で何度も連絡してくださった年配の女性に、感謝の気持ちを込めて「ご迷惑をおかけしました」と丁寧に伝えたら、「あなたみたいな人が来てくれて嬉しい」と笑顔を見せてくれました。
このやり取りは、今でも記憶に残っています。「相手に伝えたい」という本気が、脳にも深く刻まれるんだと感じました。
小刻み学習+短休憩のリズムで、知識は定着する
「20分学習+5分休憩」のサイクルが最も効率的、というのも目からウロコでした。
最近では、朝の時間を使って「脳トレ」アプリやニュースの要約を読んでインプットする習慣を始めています。タイマーをセットして20分集中→5分ぼーっとする。このリズムが心地よく、以前よりも内容が頭に残っている実感があります。
ゆっくり学ぶことは、遠回りではない
僕は専門学校時代、製図の課題に苦しんでいました。周りがどんどん進める中、僕は「これ、本当に意味あるのかな…」と焦っていました。
でも、じっくり時間をかけて仕上げた課題の方が、先生からも評価が高かった。早く終わらせることよりも、深く理解することの方が価値がある。
この本で書かれていた「ゆっくり学ぶ方が、最終的には効率がいい」という言葉に、すごく励まされました。
「脳は、自分で育てられる道具だ」
この本からの一番の学びは、「脳は鍛えればどんどん使えるようになる」ということ。
努力や成長は根性論ではなく、「使い方を知ること」なんだと気づきました。僕のように「過去に挑戦して挫折したことがある人」にこそ、この本は読んでほしいと思います。
あなたへの行動のヒント
このブログを読んでくださっている方へ。
もし今、
・やりたいことがあるけど集中できない
・何か始めても続かない
・自分に自信が持てない
そんなふうに感じていたら、まずは1日20分、自分の興味のあることを学ぶ時間を作ってみてください。
そして、休憩も忘れずに。
「今日はできた」と小さな実感を積み重ねることで、脳は「これは覚える価値がある」と判断してくれるはずです。
脳は一生、成長できます!
自分の未来を、自分の頭で変えていきましょう!
今回はここまで!
また次回のかいりおblogでお会いしましょう!
ではまた!🖐️
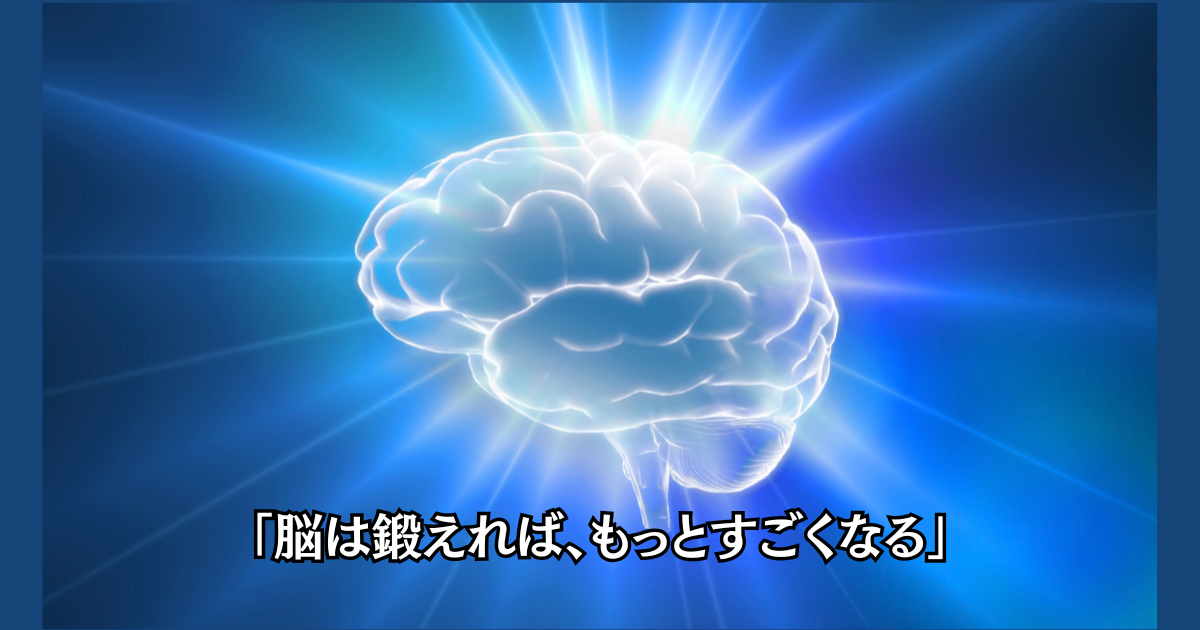
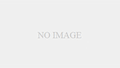

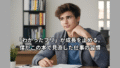
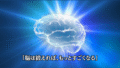
コメント