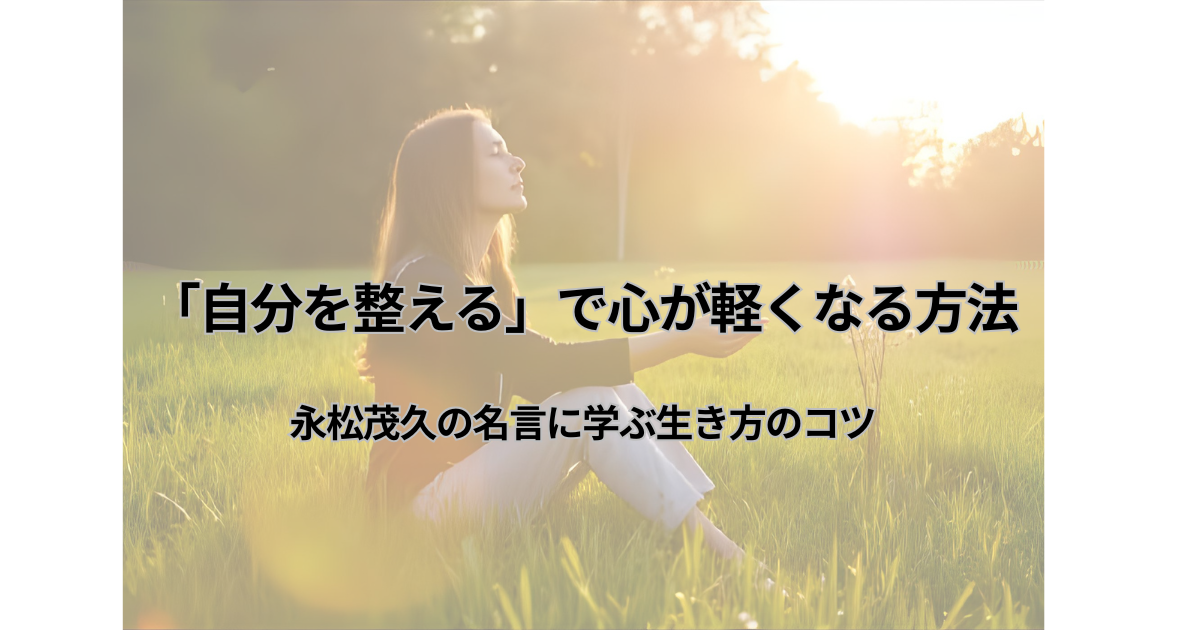
こんにちは!かいりおです 🌱
今回は、永松茂久さんの著書『自分を整える 手放して幸せになる40のこと』を読んで、僕が実際に感じたことや、自分の過去を振り返って得た学びを、皆さんと共有したいと思います!
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい
そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
この本を読んで、僕は「心の中にあるいらないもの」を抱えすぎていたことに気づかされました。何かに挑戦しようとするとき、うまくいかないことの原因は、努力や才能の不足だけではない。実は、心の状態が整っていないせいで、本来のパフォーマンスが出せていなかったというケースもあるんじゃないかと思ったんです。
この記事では、僕自身の過去の経験を交えながら、本書から学んだことをシェアします。特に、心の整理が苦手だった僕がどんなふうに少しずつ変わっていけたか、そしてこの記事を読んでくださっているあなたがどう変われるかについても触れていきます。
我慢した感情は、ただ消えることはない
本書の冒頭に書かれていた「我慢したストレスや感情は自然に消えない」という言葉。これには本当に共感しました。
僕自身、昔から周囲の目を気にする性格で、特に高校時代は監督の目ばかり気にしてプレーしていました。思いっきり打席に立てず、「ミスしたら怒られる」「結果を出さなきゃベンチだ」と、常にプレッシャーに押し潰されそうになっていました。
実はその影響もあってか、高校時代から社会人になってからも、定期的に「肺気胸(はいききょう)」になっていたんです。ストレスが体に出てしまうタイプだったんですね。
その当時は「ストレスは感じないようにしよう」と思っていたけれど、見て見ぬふりをしても、感情は消えてはくれませんでした。むしろ、気づかないうちに心の奥にたまり、ある日ドカンと爆発する。
本書では、そんな感情の蓄積が、心と体のパフォーマンスを下げる原因になると語られています。だからこそ、「心を整える」ことが、すべての土台になる。まさに、僕の過去とリンクする部分でした。
「気分が上がる選択」を、もっと大切にしていい
本の中で印象的だったのは、「気分が上がる選択をする習慣を持とう」という一節です。
僕は、これまで副業としていろいろなことに挑戦してきました。せどり、LINEスタンプ制作、動画編集、インスタ運用……。でも結局、どれも継続できませんでした。
なぜ続かなかったのかと振り返ると、それらが「ワクワクするからやってみたい」ではなく、「稼げそうだからやらなきゃ」といった“義務感”から始まっていたんですよね。
でも、心を整えるには「気分が上がる」ことを優先して選ぶことが大切。たとえば、最近は毎朝アファメーションをしたり、ジャーナリングをしたり、自分の気分が整う習慣を意識的に取り入れるようにしています。
特に、ジャーナリングは心を整えるのに最強のツールだと感じています。思ったことを紙に書き出すだけなのに、不思議と頭の中が整理されるんです。これも本書の中で推奨されている「自分ひとりでできる気分アップ法」に通じる部分です。
「自分の機嫌は自分でとる」というマインドの威力
「自分の機嫌は自分でとる」。この言葉は、僕にとって人生を変えるほどのインパクトがありました。
以前の僕は、他人の言葉に気分を左右されまくっていました。上司にきつく言われたら一日中落ち込み、野球のチームメイトから一言言われただけでずっと気にしてしまう。
でも今思うと、機嫌を人任せにしていたんです。
本書では、自分の機嫌を自分で取ることが「人生の主導権を握ること」だと語られています。たしかに、自分が上機嫌でいれば、周囲との人間関係もスムーズになるし、余計な摩擦も減る。気分がいいときほど、行動力も上がる。これは僕自身が体感した事実です。
最近は、配達中に意識して「お気に入りの音楽」をかけるようにしています。特に昔よく聞いていた野球の応援ソングや、ボウリング時代にテンションを上げていた曲を聴くと、自然と気分が上がるんです。
手放すことで、本当に大切なものが見えてくる
本書のタイトルにもある「手放す」。これは単に“モノを減らす”ということではなく、“思考や感情、情報も含めて余分なものを削る”という意味です。
たとえば僕は、「完璧を目指すクセ」がありました。高校の野球部時代も、専門学校での課題も、副業も、「100点じゃなきゃ意味がない」と思っていました。
でも結果的に、それが自分を追い込む原因になり、肩を壊したり、やる気を失ったり、諦めることにつながっていたんです。
本書では「8割できればOK」と考えることの大切さが説かれています。この考え方を取り入れるようになってからは、僕自身かなり心が軽くなりました。
今では、「とにかくブログを毎日書くこと」に集中しています。完璧な記事を書こうとすると、1記事に何日もかかってしまっていましたが、「今日はこのくらいでOK」と区切りをつけることで、結果的に継続できています。
自分を責めるのではなく、感謝を向ける
本書の中で、僕が特に心に響いたのが「過去の自分に感謝しよう」という考え方です。
僕は、施工管理の会社をたった3日で辞めたことを、ずっと引け目に感じていました。「根性がない」「社会人失格」と、自分を責める言葉ばかり浮かんできて……。
でも今考えれば、あのとき逃げたからこそ、いろんな働き方を経験し、自分がどんな仕事に向いているのかを知ることができました。そしてその道の中で、自分の「書くこと」への想いにも出会えました。
過去を責めても何も変わらない。でも、過去の自分が踏ん張ってくれたこと、決断してくれたことに「ありがとう」と言うだけで、少し心が整ってくるのを感じました。
【行動のすすめ】「心の大掃除」を始めてみませんか?
ここまで読んでくださったあなたに、ぜひおすすめしたいのは「心の大掃除」をすることです。
- 毎日5分でもいいから、感情を書き出す
- 嫌な気持ちを抱えたままにしない
- 気分が上がる行動を1つ取り入れてみる(映画・カフェ・音楽・運動など)
そんな小さな行動の積み重ねが、確実に「自分を整える力」になります。
僕も最初は、読書やジャーナリングなんて「面倒だな」と思っていました。でも、少しずつ続けるうちに「気分がいい状態の自分」で過ごせる時間が増えたんです。
後半へ続く…
後半では、「他人の評価に振り回されない考え方」「精神的コスパの良い選択」「幸せの条件とは何か?」など、さらに心に響いたテーマを深掘りしていきます。
また、「手放すこと」で人生がどう変わるのか、僕の経験も交えて紹介していきますので、ぜひ続きも読んでください!
今回はここまで!
また次回のかいりおblogでお会いしましょう!
ではまた 🌱
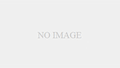

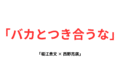
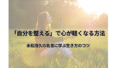
コメント