
こんにちは!かいりおです 🌱
今回は後編!
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
前編では、『サクッとわかるビジネス教養 行動経済学』を通して、「人はなぜ非合理な行動をしてしまうのか」について、僕自身の経験も交えてお話ししました。
後編となる今回は、行動経済学の学びが「マーケティング」、「マネジメント」、「自己実現」という3つの分野でどう活かせるのか、
そしてそれを踏まえて、僕がこの本からどんな一歩を踏み出そうとしているのかを掘り下げてお伝えします。
マーケティングに活かせる「人の心理を読む力」
行動経済学の知識は、マーケティングに直結します。
なぜなら、マーケティングとは「人に行動してもらう仕組みを作ること」だからです。
たとえば本書では、「極端な選択肢を提示すると、人は中間を選びやすい」という行動心理が紹介されていました。
これは「おとり効果」とも呼ばれます。
飲食店のメニューでよくある「Aセット:800円、Bセット:1200円、Cセット:1800円」という3つの価格帯があったとき、多くの人は真ん中のBセットを選びます。
高すぎず、安すぎず、ちょうど良いと感じるからです。
この知識は、副業でLINEスタンプを販売しようとしていた頃の僕にも、知っておきたかったことの一つでした。
当時、価格設定を「100円で安さをアピールすれば売れる」と単純に考えていましたが、今なら、「あえて高めの価格帯の商品を並べておいて、買ってほしいスタンプを“お得に見せる”」という工夫ができたかもしれません。
つまり、行動経済学を知ることで、「売りたい商品を、いかに自然に“選ばせるか”」という視点が持てるようになるんです。
マネジメントや人間関係にも役立つ「バイアスの理解」
次に紹介されているのが、マネジメント分野への応用です。
これは企業の上司やチームリーダーに限らず、「人と一緒に何かを成し遂げたい」すべての人に関係してきます。
その鍵になるのが、「認知バイアスの理解」です。
本書でも、「人は自分の“好き”や“正しい”を無意識に肯定してしまう」と説明されています。これを「確証バイアス」と呼びます。
僕が以前、日本郵便で委託として働いていた頃、先輩のやり方に疑問を持ちつつも、「でもこの人が正しいって言ってるんだから…」と自分の直感を無視して行動し、失敗した経験があります。
今思えば、「相手が年上だから正しいだろう」と、自分に都合の良い解釈をしていたんですね。
行動経済学を知っていれば、「あ、今、自分は確証バイアスに引っ張られているな」と気づけたはずです。
人と関わる上で、相手も、そして自分も「バイアスに影響されている」と理解することは、無駄な衝突や誤解を防ぎ、より良いコミュニケーションにつながります。
「自己実現」に活かす――“踏み出せない自分”を納得させる方法
この本で最も僕の心に刺さったのが、「自己実現」のために行動経済学をどう使うか、という視点です。
なぜなら僕自身、挑戦しては挫折を繰り返してきたからです。
インスタの運用、副業としてのLINEスタンプ制作、SNS発信。
いずれも「やってみたい!」と思って始めたものの、結果が出なかったり、自分に自信が持てなかったりして、継続できませんでした。
でも、行動経済学を学んで気づいたのは、「やめてしまうのは自分の意志が弱いからじゃない」ということ。
たとえば、「今すぐの快楽を優先してしまう傾向」は「双曲割引」と呼ばれています。
これは、将来の大きな報酬よりも、目の前の小さな報酬を選んでしまうという人間の心理。
また、最初の印象がその後の判断に影響を与える「アンカリング効果」もあります。
僕は「最初の投稿がバズらなかった=自分には才能がない」と勝手に決めつけていました。
こうした心理メカニズムを知ることで、「自分はダメなんだ」と落ち込むのではなく、「そう感じてしまう構造があるんだ」と一歩引いて捉えることができるようになったのです。
これは、挑戦を継続するうえで非常に大きな支えになります。
小さく始める勇気――行動経済学が教えてくれた「一歩の設計」
今の僕は、「また新しい挑戦を始めてみたい」と思っています。
それはブログの運営です。
この文章もその一環です。
でも、以前の僕なら「どうせまた途中で挫折するかも」「誰も読んでくれなかったらどうしよう」と不安になっていたでしょう。
だからこそ今は、「小さな成功体験を積む設計」を意識しています。たとえば…
- 1記事2000文字以上という“自分なりの達成基準”を作る
- 投稿前に、「誰かの役に立つ内容になっているか」をチェックする
- アクセス数に一喜一憂しないよう、目標を「継続」に置く
これらはすべて、行動経済学の中で紹介されていた「選択の構造を変える」考え方を応用しています。
重要なのは、「自分をだます仕組みを作ること」。
人は理屈よりも感情で動く生き物だからこそ、モチベーションや行動を維持するためには、「外部の環境を自分好みに調整する」ことが一番の近道なんです。
「自分を動かす仕組み」を考えてみませんか?
もしあなたが今、「何かを始めたいけど、続けられるか不安」「自分に向いているのかわからない」と悩んでいるなら、まずは「なぜ踏み出せないのか」を自分なりに分析してみてください。
そしてその時に、この本で学んだ行動経済学の考え方が、きっと役に立つはずです。
- あなたが不安を感じているのは、「損失回避」という心理かもしれません
- あなたが迷っているのは、「情報過多で選べない」だけかもしれません
- あなたが行動できないのは、「未来のメリットを想像しにくい」からかもしれません
すべては、「脳のクセ」なんです。
だから、無理に「自分を変えよう」としなくてもいい。
そのかわり、「自分のクセを知って、うまく付き合っていく」。
これこそが、行動経済学の一番の醍醐味だと僕は思います。
最後に:この本は、「行動に悩む人の教科書」になる
阿部誠さんの『サクッとわかるビジネス教養 行動経済学』は、僕にとって「過去の失敗を許す言葉」であり、「これからの挑戦を支えてくれる地図」でもあります。
・なぜ行動できないのか?
・なぜ選択を間違ってしまうのか?
・なぜ続けられないのか?
そんな「なぜ?」に答えてくれるこの一冊は、挑戦したいけど一歩踏み出せないすべての人に読んでほしい本です。
あなたもぜひ、日常に潜む“心理のしくみ”を知ることで、自分の行動をちょっとだけ変えてみませんか?
その変化が、きっと大きな未来につながっていくはずです。
今回はこんな感じで終わろうと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️
でたまた 🌱
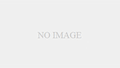


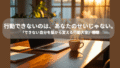
コメント
行動経済学の視点から自分の行動を振り返るのはとても興味深いですね!特に価格設定の例は、実際に試してみたくなります。確かに、高めの商品を並べることで、売りたい商品がお得に見えるのは納得です。以前の僕も同じように安さを重視しすぎて失敗したことがあるので、この考え方は参考になります。マネジメントへの応用も、上司との関係で迷ったことがある人には響きそうですね。自己実現のために行動経済学を使うという視点は、挑戦を続ける勇気を与えてくれると感じました。ただ、ブログ運営を始める際の不安について、「選択の構造を変える」という具体的な方法をもう少し詳しく知りたいです。具体的にどのようにすれば、挑戦を継続しやすくなるのでしょうか?