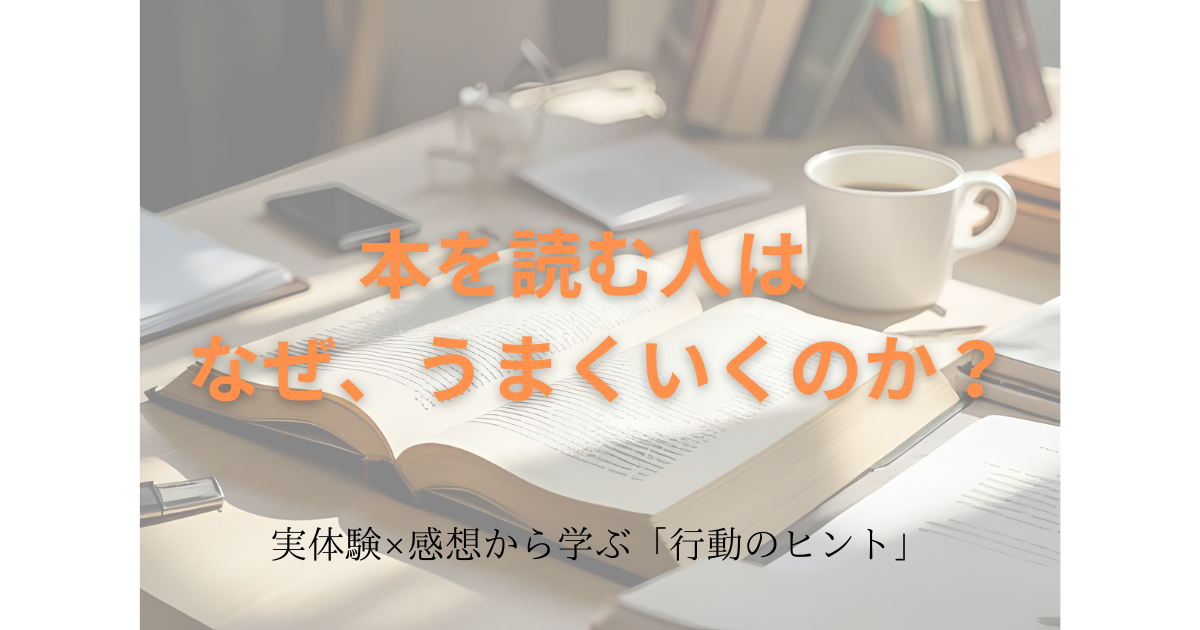
こんにちは!かいりおです 🌱
今回も、長倉顕太さんの本を読む人はうまくいくを読んだ僕の感想を皆さんに共有させていただきたいと思います!
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
今回は後編!
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
「スキミング」で効率的に本の全体像をつかむ
長倉さんは、「スキミング」という読み方を紹介しています。
目次や章の冒頭・末尾、太字などを中心に全体像を素早く把握する方法です。
僕も以前は「本は最初から最後まで丁寧に読まなきゃ」と思い込んでいましたが、社会人になってからは「時間が足りない」と感じることが多くなりました。
そこでスキミングを取り入れてみたところ、短時間で「この本はこういう内容なんだな」と全体をつかめるようになりました。
そのうえで、「ここはもっと深く知りたい」と思った部分だけじっくり読む――この方法なら、忙しい人でもたくさんの本に触れることができます。
「トリガー行動」で習慣化を加速させる
本書では、「トリガー行動」が習慣の定着率を高めると紹介されています。
僕の場合、毎朝のルーティンの中に「読書」を組み込むことで、自然と本を読む習慣が身につきました。
たとえば、アファメーションや瞑想、ジャーナリングを終えたら、その流れで読書を始める――これが僕の「トリガー行動」です。
最初は「今日は忙しいからやめておこう」と思う日もありましたが、ルーティンの中に組み込むことで「とりあえず本を開く」ことが当たり前になりました。
習慣化したいことがある人は、何か別の習慣とセットにする「トリガー行動」を意識してみてください。
「好きな部分の引用」と「自分の気づき」を書く
本を読んだら、印象に残った部分を引用し、自分の気づきをノートやSNSに書く
これも本書でおすすめされている方法です。
僕も読書ノートやブログで「このフレーズが響いた」「自分はこう感じた」とアウトプットするようにしています。
たとえば、「情報が先で現実が後」という言葉を引用し、「自分も本やネットで知ったことを実践して現実が変わった経験がある」と書いてみる。
こうすることで、ただ読むだけよりも記憶に残りやすくなり、自分の考えも整理されます。
SNSでアウトプットすることで思考が整理される
僕はブログで読書の感想や気づきを発信するようにしています。
最初は「誰も読んでくれないんじゃないか」「ちょっと恥ずかしいな」と思っていましたが、アウトプットを続けるうちに「自分の考えが整理される」「新しい視点をもらえる」といったメリットを感じるようになりました。
また、SNSで発信することで「自分の理解が深まる」「記憶定着率が高まる」と本書にも書かれています。
実際、僕もアウトプットすることで「この本の本質は何だったんだろう?」と考えるようになり、より深く内容を理解できるようになりました。
「小さな成功体験」が次のモチベーションを生む
本書で紹介されている「小さな成功体験が次へのモチベーションとなり、好循環を生み出す」という考え方も、僕の実体験と重なります。
たとえば、毎朝のルーティンを1週間続けられたとき、「自分にもできた!」という自信が生まれます。
その自信が「もっと続けてみよう」「新しいことにも挑戦してみよう」というモチベーションにつながります。
僕は副業や新しい仕事に挑戦しては挫折することも多かったですが、「まずは1日やってみる」「1週間続けてみる」といった小さな目標をクリアすることで、少しずつ自信を積み重ねてきました。
「一歩踏み出す勇気」を持とう
僕のブログは「何かに挑戦したい人になにか一歩踏み出せるように」というコンセプトで運営しています。
もし今、「新しいことに挑戦したいけど不安だ」「自分にはできないかもしれない」と感じている人がいたら、ぜひこの本を読んでみてください。
本を読むことで、「知らない世界」に触れ、自分の可能性を広げることができます。
そして、読んだことを「行動」に移すことで、人生は少しずつ変わっていきます。
大きな一歩でなくてもいい。
まずは「本を1冊読んでみる」「気になったことを調べてみる」「SNSで感想を発信してみる」
そんな小さな一歩から始めてみてください。
僕自身、たくさんの失敗や挫折を経験してきました。
でも、そのたびに「新しいことを知る」「行動してみる」ことで、少しずつ前に進んできました。
あなたもきっと、何か新しい一歩を踏み出すことができるはずです。
「知識が豊富な人」を目指すことの価値
本書の中で繰り返し強調されているのが、「人は知識が豊富な人を探すもの」というメッセージです。
僕自身、学生時代から社会人になるまで、さまざまな現場やバイトでいろんな人と出会ってきました。
その中で「この人頼りになるな」「話していて面白いな」と思う人は、やっぱり知識が広くて、どんな話題にも対応できる人でした。
たとえば、草野球の仲間でも、野球だけでなく仕事や趣味、時事ネタに詳しい人は自然とみんなの中心になります。
僕も「どうせなら自分もそうなりたい」と思い、本を読む習慣をつけるようになりました。
知識が増えると、会話の幅が広がり、人間関係も豊かになります。
配達の仕事でも、ちょっとした雑談でお客様と盛り上がれたり、職場の人と打ち解けやすくなったりするのは、やっぱり「知っていること」が多いからこそだと実感しています。
また、知識が豊富だと「選択肢」も増えます。
僕が副業に挑戦したときも、ネットや本で調べて知識を得ていたからこそ、「次はこれをやってみよう」と新しい一歩を踏み出せました。
知識は自分の「武器」になり、人生のあらゆる場面で役立ちます。
もし「自分には特別なスキルがない」と感じている人がいたら、まずは本を読むことから始めてみてください。
知識を積み重ねることで、必ず自信につながります。
「完璧」よりも「目的意識」を持つことの重要性
完璧主義を捨てて、目的意識を持つ
これは僕にとっても大きな気づきでした。
たとえば、ブログを書くとき、「完璧な記事を書かなきゃ」と思うと手が止まってしまい、なかなか投稿できません。
でも、「今日は誰か一人でも勇気づけられればいい」「自分の気づきを残そう」と目的を明確にすると、気軽に書き始められるようになりました。
専門学校時代も、最初は「完璧な図面を描かないと」と思い込んでいました。
でも、先生から「まずは全体像をつかんで、目的に合わせて修正していけばいい」とアドバイスをもらったことがあり、肩の力が抜けたのを覚えています。
配送の仕事でも、最初は「絶対にミスしないように」と緊張していましたが、「お客様に安全に荷物を届ける」という目的を意識することで、失敗してもすぐに切り替えられるようになりました。
完璧を目指すのではなく、「なぜそれをやるのか」「自分は何を伝えたいのか」という目的意識を持つことで、行動のハードルがぐっと下がります。
これは、何か新しいことに挑戦したい人にとって、とても大切な考え方だと思います。
失敗を恐れず、まずは「目的」を明確にして一歩を踏み出してみてください。
このように、『本を読む人はうまくいく』には、今の時代を生き抜くためのヒントがたくさん詰まっています。
知識を増やし、目的意識を持って行動する――その積み重ねが、きっとあなたの人生をより豊かにしてくれるはずです。
ぜひ、この本を手に取って、自分だけの「新しい一歩」を踏み出してください。
あなたの挑戦を、心から応援しています!
『本を読む人はうまくいく』をおすすめする理由
最後に、この本をまだ読んでいない方へ。
長倉顕太さんの『本を読む人はうまくいく』は、単なる「読書のすすめ」ではありません。
「知ること」「行動すること」「環境に適応すること」「完璧主義を捨てること」
現代を生き抜くために必要な「考え方」と「行動のヒント」がぎゅっと詰まった一冊です。
僕のように「いろんなことに挑戦しては失敗ばかり…」という人にも、「これから何か始めてみたい!」という人にも、きっと大きな気づきと勇気を与えてくれるはずです。
読書が苦手な人でも、スキミングやアウトプットのコツが具体的に書かれているので、「まずは1冊読んでみよう」と思える内容になっています。
あなたもぜひ、『本を読む人はうまくいく』を手に取って、「新しい自分」に出会う一歩を踏み出してみてください。
きっと、あなたの人生が少しずつ動き出すはずです。
今回はこんな感じで終わろうと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️
でたまた 🌱
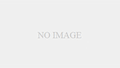

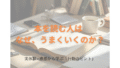
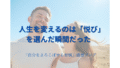
コメント