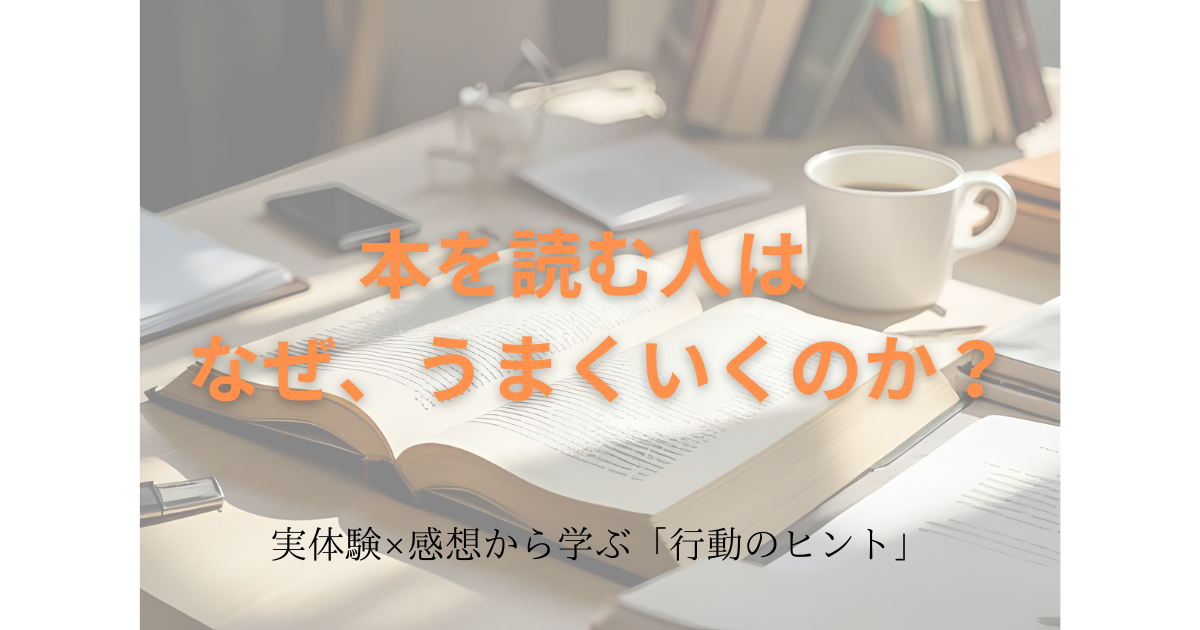
こんにちは!かいりおです 🌱
今回は、長倉顕太さんの本を読む人はうまくいくを読んだ僕の感想を皆さんに共有させていただきたいと思います!
この本はこの前の2025年の6月3日に発売されたばかりの新刊で、僕もさっそく買って読ませていただきました!🤩
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
「やりたいことがあるけど、なかなか一歩を踏み出せない」
そんなふうに感じているあなたへ。
今回は、長倉顕太さんの『本を読む人はうまくいく』を読んで、僕が感じたこと、そして実際に行動する中で見えてきたものを、正直にお話ししていきたいと思います。
「知ること」の連鎖が人生を変える
この本の中で特に印象的だったのは、「知れば知るほど、知らないことに気づく」という一文です。
僕自身、建築や配達、さまざまなアルバイト、副業など、いろんな仕事を経験してきました。
そのたびに「自分はまだまだ知らないことだらけだな」と痛感してきました。
たとえば、施工管理の会社に就職したとき、3日でやめることになったのですが、その経験から「自分に合う仕事って何だろう?」と考えるきっかけになりました。
郵便や運送の委託業務、せどりやLINEスタンプ作成、インスタ運用など、次々と新しいことに挑戦しては挫折も経験しました。
でも、そのたびに「知らなかった世界」「自分に足りないもの」「新しい可能性」に気づくことができたのです。
本を読むことで、実際に行動しなくても、たくさんの「知らない世界」に触れることができます。
たとえば、僕は最近毎朝のルーティンに読書を取り入れていますが、1冊読むごとに「今までの自分の考え方は狭かったな」と思うことが多いです。
本の中の登場人物や著者の体験談を通じて、「自分もこうしてみよう」「こんな考え方もあるんだ」と思えるようになりました。
「選択」よりも「選んだ後」が大事
長倉さんは「どっちを選んだっていい。選んだ後が重要」と書いています。
僕も進路や仕事、副業などで迷ったとき、「どっちが正解なんだろう」と悩むことが多かったです。
でも、どちらを選んでも、結局は「選んだ後にどう行動するか」が大切だと今は思います。
たとえば、建築の専門学校を卒業した後、施工管理の会社に入ったもののすぐに辞めてしまいました。
そのときは「失敗した」と落ち込みましたが、郵便や運送の委託の仕事を通じて、「自分は人と話すよりも黙々と作業するほうが向いている」と気づきました。
もしあのとき、辞めることを「失敗」と決めつけて何も行動しなかったら、今の自分はなかったと思います。
「情報が先で現実が後」――だからこそ本を読もう
「情報が先で現実が後」という言葉も、僕にはとても響きました。
今の時代、ネットやSNSでたくさんの情報が手に入りますが、「自分に必要な情報」を選び取る力が大切だと感じます。
本を読むことで、その「選び取る力」が鍛えられる気がします。
たとえば、僕は副業でせどりやLINEスタンプ作成、インスタ運用などを試してみましたが、どれも簡単にはうまくいきませんでした。
でも、その過程で「どうやったら売れるのか」「どうやったら人の目に留まるのか」といった情報を集めて実践することで、少しずつ「現実」が変わってきたのです。
本で学んだことを「すぐに現実に反映させる」ことは難しいですが、知識が増えることで「次はこうしてみよう」という行動につながります。
「環境適応能力」を高めるには「怖いけど、おもしろそう」を選ぶ
僕はこれまで、いろんな仕事や副業、アルバイトに挑戦してきました。
正直、どれも「怖いけど、おもしろそう」と思って始めたものばかりです。
たとえば、出会い系アプリでマルチに引っかかった経験もあります。
今思えば「なんであんなことに…」と苦笑いですが、これも「知らない世界」に飛び込んだ結果です。
長倉さんは、「環境適応能力こそが、これからの人生を左右する」と言っています。
僕もいろんな環境に身を置いてきたことで、「どんな状況でもなんとかなる」という自信がつきました。
怖いけど、おもしろそう
この気持ちを大事にしていれば、どんな環境でも適応できる力が身につくと思います。
「行動」こそが人生を変える
結局、人生は「行動がすべて」だと僕も思います。
本を読んで学ぶだけではなく、「実際にやってみる」「失敗してみる」「また挑戦してみる」
この繰り返しが、自分の人生を大きく変えていくのだと実感しています。
たとえば、僕は毎朝アファメーションや瞑想、ジャーナリング、読書、ブログ記事作成をルーティンにしています。
最初は「こんなこと意味あるのかな?」と思っていましたが、続けていくうちに「自分の考えが整理される」「新しいアイデアが浮かぶ」「行動するハードルが下がる」など、少しずつ変化を感じるようになりました。
「日常に非日常を取り入れる」ことで人生が動き出す
長倉さんは「日常に非日常を取り入れるべし」とも書いています。
僕の場合、普段やらないことをやってみる、行ったことのない場所に行ってみる、知らないジャンルの本を読んでみる
――こうした「非日常」の体験が、人生を面白くしてくれると感じています。
仕事でも、普段は配達のルートを変えてみたりすることで、思わぬ発見があったりします。
こうした「ちょっとした非日常」が、毎日をワクワクさせてくれるのです。
「自分が知らないことを知っている人」に惹かれる
人は「自分が知らないことを知っている人」に惹かれる――これも本当にその通りだと思います。
僕も、いろんな仕事や副業を通じて、「この人すごいな」「こんな考え方があるんだ」と思う人に出会ってきました。
そういう人たちの話を聞くことで、自分の世界がどんどん広がっていきます。
逆に、自分が本を読んで得た知識や経験を誰かに話すことで、「そんなこと知らなかった!」と驚かれることもあります。
そういうとき、「本を読んでいてよかったな😌」と感じます。
「好き嫌い」ではなく「新しいこと」に挑戦する
僕はこれまで、「好きだからやる」「嫌いだからやらない」といった基準で行動してきたことが多かった気がします。
でも、長倉さんの「好き嫌いではなく、新しいことをやれ」という言葉を読んで、「もっといろんなことに挑戦してみよう」と思うようになりました。
たとえば、今まで読んだことのないジャンルの本を手に取ってみたり、普段は行かない場所に出かけてみたり、苦手だと思っていたことにもチャレンジしてみたり。
そうすることで、「自分の可能性」がどんどん広がっていくのだと思います。
「多様な人間関係」「多様なジャンル」の大切さ
僕は学生時代からいろんなバイトを経験してきました。
コンビニ、Uber Eatsの配達員、引越し、野菜キット作りなど、全然違う業界で働くことで、いろんな人と出会い、いろんな価値観に触れることができました。
長倉さんが言うように、「多様な人間関係を持つ人ほど、環境変化にも柔軟に適応できる」と実感しています。
また、「多様なジャンルをつまみ食いする方が現代社会では有用」というのも納得です。
僕も、建築や運送、せどり、SNS運用など、いろんなジャンルを経験してきたことで、「どんな仕事でもなんとかなる」という謎の根拠のない自信がつきました。💪🤭
「完璧主義を捨てる」ことの重要性
僕はもともと「完璧主義」なところがあって、「うまくできないならやらないほうがいい」と思ってしまいがちでした。
でも、長倉さんの「完璧主義を捨てる」「完璧よりも目的意識を持つ」という言葉を読んで、「とにかくやってみる」「目的を持って行動する」ことの大切さに気づきました。
たとえば、ブログ記事も「完璧な文章を書こう」と思うと手が止まってしまいますが、「誰かの役に立つ情報を届ける」という目的を持つことで、気軽に書き始められるようになりました。
新しい世界は、ほんの小さな行動の先にあります。
本を手に取ってみる、知らないジャンルに触れてみる、やったことのないことに挑戦してみる。
そんな一歩が、あなたの未来を変えるかもしれません。
まずは今日、1ページだけでも読んでみませんか?
きっと、あなたも「本を読む人はうまくいく」と感じられるはずです📚
気になった方は、ぜひこの一冊を手に取ってみてください!
今回はここまで!
また次回のかいりおblogでお会いしましょう!
ではまた 🌱
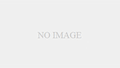

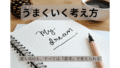
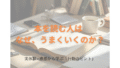
コメント