
こんにちは!かいりおです 🌱
今回は、相良奈美香さんの『行動経済学が最強の学問である』を読んだ僕の感想を皆さんに共有させていただきたいと思います!
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
「何を選ぶかは自分次第だ」
そう思っていた時期が、僕にもありました。
でも、この本『行動経済学が最強の学問である』を読んで、自分の選択がどれだけ“感情”や“環境”に左右されていたのかを知り、衝撃を受けました。
そして、「僕たちが合理的な判断をしていると思い込んでいるその瞬間こそ、非合理のオンパレードだった」という事実に、目が覚めるような気持ちになったんです。
疲れているときほど「思考」は機能しない
今、僕はヤマト運輸の委託ドライバーとして働いています。
荷物の量は日によってバラバラ。
繁忙期や雨の日、配達先が入り組んだ場所に集中すると、それだけで心も体もぐったりしてしまいます。
そんなある日、クレームを入れてきたお客さんに感情的に対応しそうになったことがありました。
普段なら冷静に「申し訳ありません」と言えるところなのに、「あれ?なんでこんなにイラついてるんだ?」と、自分の変化に気づけなかった。
本書の中で、「人は疲れている時や時間がない時、感情でものごとを判断してしまう」とありましたが、まさにその通りです。
つまり、“疲れているときこそ判断をしてはいけない”ということ。
それ以降、僕は仕事が終わってから大事な決断をするのをやめるようにしました。
たとえば、LINEスタンプの制作を副業としてやっていた頃は、夜に「もうやめようかな」と思っていたことがよくありました。
でも今ならわかる。
あれは、疲れていて「正常な判断」ができていなかっただけだったのです。
「確証バイアス」は、過去の挫折も美化してしまう
僕には、過去にInstagramの運用にチャレンジしたことがあります。
最初はワクワクして、いろいろ試行錯誤していました。
でも、いいねが伸びない、フォロワーが増えないという理由で、だんだんネガティブな情報ばかり検索するようになっていきました。
「インスタで成功するのは一部の人だけ」
「アルゴリズムが変わったから今はもう難しい」
これらの言葉を見て、「やっぱりダメだったんだ」と勝手に納得してしまったのです。
まさにこれが、「確証バイアス」。
つまり、「うまくいかない」と思ったときに、それを裏付ける情報ばかりを集めて、自分を正当化してしまっていたんです。
本書では、「人は思い込んだことを正当化するために都合の良い情報ばかり集めてしまう」と書かれていて、僕はまさにそれをやっていたなと気づかされました。
見えない力が「選択」を誘導している
もう一つ驚いたのが、“状況”がいかに僕たちの意思決定を歪めているかということです。
たとえば、僕は出会い系アプリでマルチ商法に引っかかった経験があります。
今思えば、あの時は「仲間がいる雰囲気」や「ちょっといいカフェでの面談」、何より「相手が親身に自分の夢を応援してくれた感じ」が、僕の判断を狂わせていました。
これはまさに、「状況が人の判断を操作する」典型です。
冷静になれば「うまい話には裏がある」なんて誰でも知っていること。
でも、その場の空気や雰囲気、人間関係の構築に心を動かされて、非合理な選択をしてしまったわけです。
「多すぎる選択肢」はむしろ人を迷わせる
引越しやアルバイトなど、いろんな仕事を経験してきた僕ですが、その中で最も迷ったのが“次の仕事を決めるとき”でした。
選択肢が多いと、「本当にこれでいいのかな?」という疑念が何度も浮かんでしまう。
たとえば転職サイトを見ていると、条件の良い会社がズラリと並びますが、どれも良さそうに見えて決めきれないんです。
本書には、「多すぎる情報や選択肢は、意思決定を妨げる」とありました。
これは本当にその通り。
選択肢が多いことが“自由”ではなく、“不自由”になるというパラドックスを、僕自身の人生で実感していました。
だからこそ最近は、「どうでもいいことはテキトーに決める」ようにしています。
たとえば、朝飲むコーヒー、配達のルート組み、昼ごはんのおかず。
これらは“判断のエネルギー”を奪うので、あらかじめルールを決めておくようになりました。
信じてくれる誰かがいる。それだけで、人は「自分を信じてみよう」と思える。
僕は、ずっと自信が持てない人間でした。
建築設計科を出たのに3日で仕事を辞めたこと。
その後も「安定した正社員」にはならず、委託ドライバーとして働く日々。
学生時代の同級生がキャリアを積んでいく中で、どこか自分だけが取り残されている気がしていました。
「俺って、結局なにも続かないんじゃないか」
そんなふうに思い込んでいたある日、草野球チームの先輩が、ふとこんな言葉をくれました。
「ピッチャーやってみたら?投げ方とか、すごい綺麗だし」
それまでは内野ばかりやってきた僕にとって、ピッチャーなんて中学生のころに少しやっていたくらい。
でも、不思議とその言葉は胸にスッと入ってきました。
なぜなら、「誰かが自分を評価してくれた」という事実が、心の奥をあたためてくれたから。
そこから、少しずつですがピッチャーとしての練習を始め、今ではマウンドに立つ機会も増えてきました。
あなたも「思い込み」から抜け出せる
この本を読んで学んだ最大のことは、「人は合理的なようでいて、実はかなり非合理な生き物」だということ。
でも、それを知っているか知らないかで、人生の選択に大きな差が出てくると思います。
・疲れているときは決断しない
・選択肢は絞った方がいい
・「確証バイアス」に気づいたら、反対意見にも目を向ける
・誰かの「あなたならできる」を素直に受け取る
この小さな意識の変化だけでも、日々の行動は変わっていきます。
だからこそ、「何かに挑戦したい」と思っているあなたにこそ、まずは“自分の選択が感情や環境に左右されている”という前提を持ってほしいです。
【最後に】選択は武器になる
『行動経済学が最強の学問である』は、ただの理論書ではありません。
人生の中で迷ったとき、誰かに流されそうになったとき、自分の選択を正しく導くための“武器”になる一冊です。
「選択する力」を強くしたいなら、まずは“人がどう選ばされているか”を知ることから始めましょう。
きっと、読後には「この本に出会えて良かった」と思えるはずです。
今回はここまで!
また次回のかいりおblogでお会いしましょう!
ではまた 🌱
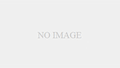

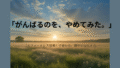

コメント