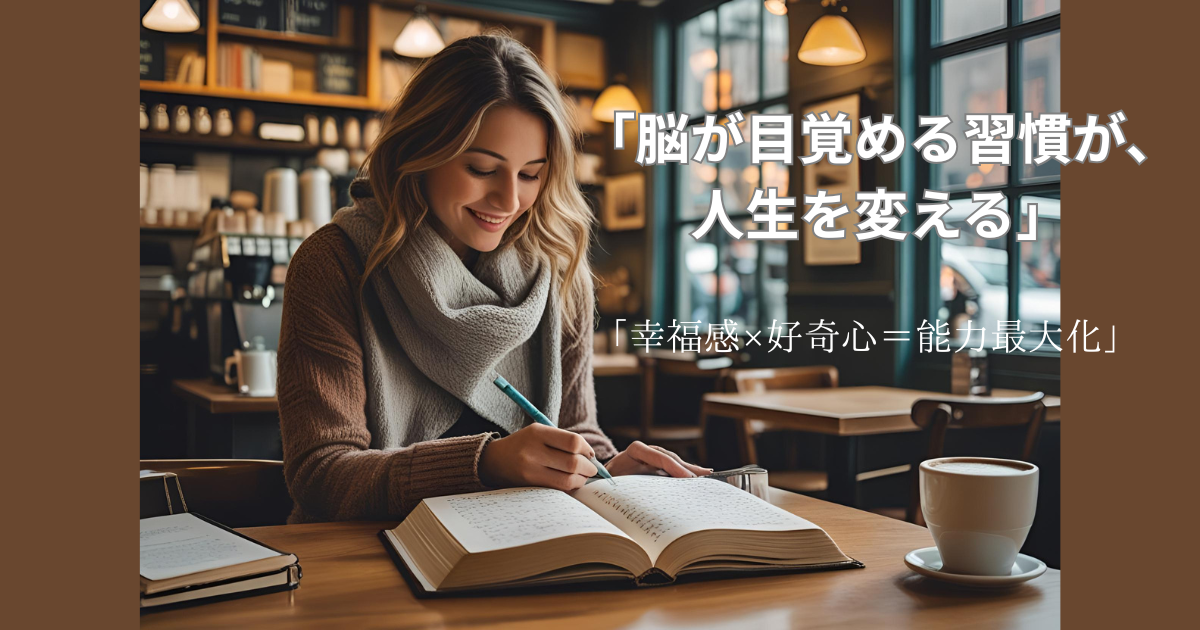
こんにちは!かいりおです 🌱
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
今回は後編!
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
前回の感想文では、「幸せな選択」が脳を活性化させるという視点から、僕自身の経験や考え方の変化についてお伝えしました。
今回は、より具体的に「脳が目覚めるたった1つの習慣」が、どう日々の行動に活かされるのか。
そして、僕が実際にやっている“朝のひとり時間”の工夫がどのように本の内容とリンクしているのかを掘り下げていきます。
「朝活」は最高の脳トレである
この本では、脳が最も活性化する時間帯は「午前中」、特に「起床から2〜3時間後」だと紹介されています。
これは僕にとって大きなヒントでした。というのも、僕が朝のルーティンを始めたのは「何かを変えたい」と思ったのがきっかけでしたが、最初はただの気合と根性で始めたものです。
でもこの本を読んで、「朝に活動すること」そのものが科学的にも理にかなっていると知ったとき、やっと自分の行動に意味を見出せた気がしました。
特に、ドーパミンやセロトニンの分泌をコントロールするには朝日を浴びること、軽く体を動かすことが非常に有効だと書かれていて、「朝活=脳を整える最強の時間帯」だという意識が芽生えました。
僕の朝ルーティンと「脳の整え方」の関係
今の僕の朝活ルーティンは次のとおりです。
- 4:50 起床
- 5:00 アファメーション(肯定的な言葉を唱える)
- 5:05 瞑想(5分間)
- 5:10 ジャーナリング(頭の中の整理)
- 5:20 読書(10分)
- 5:30 朝ごはん(納豆ごはん)
- 6:00 ブログ記事作成(1時間)
こう書くとストイックに見えるかもしれませんが、最初は2つの習慣から始めました。
特に効果を感じたのは「アファメーション」と「ジャーナリング」です。
これは本にも通じていて、「ポジティブな言葉を口にすること」は脳にとって“刺激”になり、脳内の報酬系が活性化すると書かれていました。
また、ジャーナリングは「考えを“見える化”する」行為で、情報を整理する前頭前野を使うため、脳のウォーミングアップとして非常に効果的だと実感しています。
情報の「選び方」こそが脳の差を生む
本では、「情報をどう選び、どう意味づけするか」が脳の成長に直結すると語られていました。
この話も、僕のブログ運営や読書習慣と直結しています。
たとえば、以前の僕はスマホでニュースやSNSを漠然と眺めて過ごしていました。
でもそれは、脳にとって「受動的」な時間で、実は思考が鈍くなる要因でもあったと気づきました。
今では「自分の将来像に必要な情報」「今の自分がワクワクする情報」だけに絞ってインプットするように意識しています。
たとえば、行動経済学や脳科学、習慣化など、自分の朝活やブログと関連の深いテーマに集中して読むようにしています。
これは本の中で語られていた「情報を自分の未来とリンクさせることが脳のモチベーションを高める」という内容とまさに一致します。
つまり、ただ情報を受け取るのではなく、「なぜそれを知りたいのか?」を自分の中で問い続けることが、脳にとって最も刺激的な学習方法なのです。
僕の朝活が「楽しく続けられる」理由
よく「どうやって毎日朝早く起きられるの?」と聞かれます。
正直に言うと、最初は寝坊する日もありましたし、継続にはかなりの試行錯誤がありました。
でも今は「気合」ではなく、「気持ちよさ」で続けられています。
なぜなら、朝活のひとつひとつが「楽しいから」。
これは本にもあった通り、「楽しいことは継続できるし、脳のパフォーマンスも上がる」からです。
朝に「今日の自分に期待する言葉を言う」と、それだけで一日がポジティブに始まります。
ブログで自分の想いを綴ると、それが誰かの背中を押すこともあります。
こうした「自分の行動が、自分と誰かの未来につながる」感覚は、何よりのモチベーションになります。
「人生を変える」は、1日の変化の積み重ね
本書の中で、脳の成長には「継続的な刺激」が必要だと書かれていました。
これはスポーツと同じで、1日だけ100球投げただけではピッチングは上達しません。
むしろ、毎日コツコツと投げ続けた積み重ねが、自分の変化をつくっていく。
ブログを書くのも同じです。
1日書かないだけで、言葉が出てこなくなる。
でも、毎日少しでも書いていると、言葉も思考も自然と“回る”ようになっていく。
つまり、「今日の習慣」が脳にとっての栄養であり、それが未来の自分の可能性をつくる。
好奇心を思い出させてくれた「草野球」の時間
僕にとって、草野球はただの趣味ではなく、好奇心と幸福感を同時に満たしてくれる貴重な時間です。
今でもピッチャーやショートとしてマウンドや守備に立つとき、純粋に「楽しい」「もっと上手くなりたい」と心から思えるんです。
本書では、「好奇心を持って生きることが、脳を活性化する鍵だ」と書かれていましたが、これは実感として本当にその通りです。
草野球をしていると、試合の駆け引きや仲間との会話、体を動かす爽快感など、さまざまな刺激が一気に脳を活性化させてくれる感覚があります。
また、野球をしているときは嫌なことを忘れられるだけでなく、不思議と新しいアイデアも浮かびやすくなります。
これは、まさに脳がリラックスしながら情報を整理している状態なのかもしれません。
読んでくれているあなたにも、子どもの頃に夢中になったこと、ワクワクした記憶がきっとあるはずです。
日常に追われると、そういった「好奇心の種」を忘れてしまいがちですが、今一度、時間をとって思い出してみてください。
それはきっと、あなたの脳を目覚めさせるスイッチになるはずです。
「楽しんでる人」が人間関係を変える
社会人になってから特に痛感するのが、人間関係の難しさです。
どんな職場でも、気が合う人もいれば、ストレスを感じる相手もいます。
僕自身、配達の仕事をしていて、配達先やドライバーとのやりとりで心が沈む日もありました。
でもある日、いつも笑顔で接してくれる先輩がこんなことを言ってくれました。
「どうせ同じ仕事するなら、楽しんだほうが得だよ」って。
そのときは何気ない言葉に聞こえたけど、今ではその意味がよく分かります。
本書には、「クリエイティブな職場を作るには、トップが人生を楽しんでいることが不可欠」とありました。
つまり、人生を楽しんでいる人は、その空気を周囲に伝播させる力があるということです。
僕が出会った先輩も、まさにその例でした。
あなたがもし、「職場の雰囲気が重い」「人間関係がうまくいかない」と悩んでいるなら、まずは自分が楽しんでいることを増やしてみてください。
小さなことでいいんです。
たとえば昼休みに好きな音楽を聴く、帰り道に寄り道をする、週末に好きなことに没頭する。
そんな小さな「楽しみ」が、やがて自分の心を明るくし、周囲にもポジティブな影響を与えていきます。
読者のあなたへ:変化は小さな1分から始まる
もし「朝が苦手」「続かない」と思っている方がいたら、無理をしなくてもいいんです。
僕も最初から完璧ではありませんでした。
むしろ、最初の一歩は「今日、1分だけ早く起きてみる」くらいで十分です。
その1分で、窓を開けて朝日を浴びてみるだけでも、脳は「今日の自分はちょっと違うぞ」と反応します。
たったそれだけで、脳がポジティブに目覚めるきっかけになるんです。
「やらなきゃ」ではなく、「ちょっとやってみたい」から始めればいい。
本書の提案する「脳を育てる習慣」は、そのくらいシンプルで、やさしくて、でも確実に変化をくれる方法ばかりです。
今回はこんな感じで終わろうと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️
でたまた 🌱
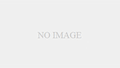


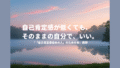
コメント