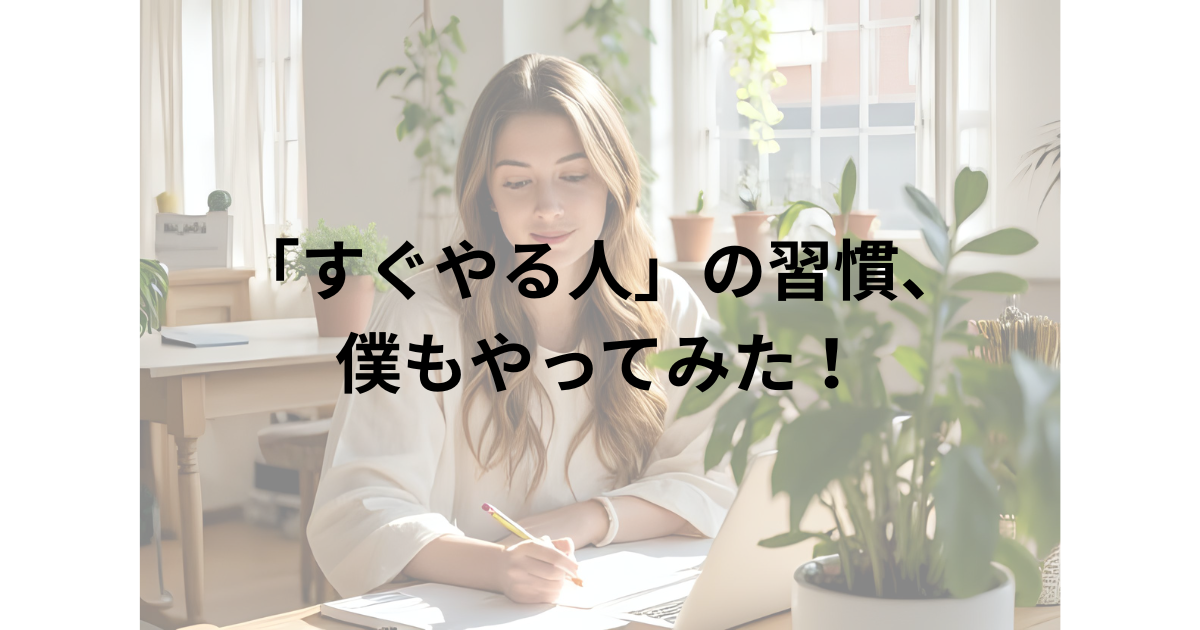
こんにちは!かいりおです 🌱
今回も、塚本亮さんの「すぐやる人」と「やれない人」の習慣を読んだ僕の感想を皆さんに共有させていただきたいと思います!
このブログでは、実際に僕が読んだ本の感想を中心に発信しています。
「何かに挑戦したい」と思っているあなたが、最初の一歩を踏み出せるようなきっかけを届けたい――そんな想いを込めて運営しています。
新しいことに挑戦したい方の背中を、そっと押せるようなブログを目指しています。
今回は後編!
それではさっそくぅぅ、やっていきまshow!👉
この本で最も印象的だった言葉の一つが、「人間は感情の生き物であるということを受け入れること」です。
僕自身、何か新しいことに挑戦するとき、頭では「やったほうがいい」と分かっていても、どこかで「不安」「面倒くさい」「失敗したらどうしよう」といった感情にブレーキをかけられてしまうことが多々ありました。
たとえば、せどりに挑戦したとき。
商品を仕入れる前に、「本当に売れるのか?」と不安になって何時間も悩んだ末、動けなくなったことがあります。
インスタ運用も、何度も投稿のアイデアを考えながら、「どうせ見られないだろ」と自己否定のループにはまり、結局アカウントは放置。
当時の僕は、“行動できない理由”を「自分に向いてない」「自信がない」と思っていましたが、実際は「感情を認めてあげてなかった」んだと思います。
この本には、「感じたことをどんどん書き出すことで、自分の中から取り出してあげることが大切」とも書かれています。
だから今の僕は、毎朝ジャーナリングの中で、もやっとした感情をそのままノートに書いています。
「怖い」「やりたくない」「なんかだるい」
こんなネガティブな感情も、文字にして吐き出すことでスッキリするし、そのあとに「じゃあどうすれば気が楽になるだろう?」と建設的に考えられるようになりました。
行動するためには、感情を押し殺すんじゃなくて、受け入れて解放することが大事。
これは僕にとって、すぐやるための土台づくりです。
自信は「実績」より「自己信頼」から生まれる
塚本さんの「自信さえ持っていれば、実績はあとからついてくる」という言葉も、とても勇気をもらえるものでした。
かつての僕は、「実績ができてからじゃないと自信なんか持てない」と思っていました。
けれどよくよく考えると、高校時代に野球部でレギュラーを勝ち取ったときも、最初から実績があったわけじゃないんですよね。
「俺ならできるはずだ」と信じて毎日素振りして、少しずつ成果が出て、結果的にレギュラーになれた。
順番が逆なんです。
副業で失敗したときも、うまくいかなかったことを悔やんでばかりでしたが、「あのとき挑戦したから、今ブログを書いてるんだ」と気づいたとき、自分の過去すら肯定できるようになりました。
自信とは、過去の積み重ね以上に、「これからの自分を信じられるか」だと思います。
もし今、「自信がないから動けない」と悩んでいる人がいたら、ぜひこの言葉を届けたいです。
“実績が自信を作るんじゃなく、自信が実績を引き寄せる”。
信じて一歩踏み出せば、少しずつ道は開けていきます。
ライバルを応援できる人が一番強い
もうひとつ、心に残ったのが「ライバルを応援することで、自分をもっと高めることができる」という視点です。
これって、一見すると自己犠牲のように思えますが、実はまったく逆。
僕もブログを始めたばかりの頃、他の発信者のアカウントを見るたびに「すごいな、羨ましいな」と思っていました。
でもあるときから、「この人の発信、めちゃくちゃいいな」と素直にリスペクトするようにしたんです。
そうすると、「じゃあ自分だったらどう表現するかな?」と前向きに考えることができるようになって、モヤモヤがスッと消えていきました。
人を羨んで止まるか、人を見て進むか。
この違いが、自分を伸ばせるかどうかの分かれ道なのだと思います。
そして何より、応援の気持ちを持つと、自分自身の言葉にも優しさが乗ってくるんですよね。
発信する側として、これはすごく大事なことだと感じています。
アウトプットを続けるから、インプットも深まる
「すぐやる人」は、マネすることをいとわないし、アウトプットを前提にインプットしている。
これもめちゃくちゃ共感しました。
僕が最初にブログを書いたとき、「自分の言葉で伝えるのが難しい」と感じていました。
だけど今では、本を読むときに「これをどう伝えよう?」という視点で読み進めるので、以前よりも理解力が格段に上がっています。
これはまさに、「アウトプットがインプットの質を変える」ことの証拠です。
最初はうまく書けなくてもいい。
続けていくことで、自然と視点や言葉の引き出しが増えていきます。
だからこそ、「学んだらアウトプット」を意識することは、成長に欠かせないプロセスです。
モノが少ない方が、行動力は高まる
「モノを持つことは、脳に大きなストレスを与える」という言葉も、かなり刺さりました。
以前の僕は、服や本、飲み物など、とにかく「備え」がないと不安で、部屋の中がモノで溢れていました。
でも、必要最低限だけを残して手放してみたら、思考がクリアになって、ブログも集中して書けるようになったんです。
あれもこれも、となると、選択肢が多すぎて“行動の出力”が分散してしまうんですよね。
持ち物を減らすことは、行動のハードルを下げることにつながります。
「すぐやる人」になりたいなら、まずは部屋の整理から始めるのも効果的かもしれません。
「断ること」が前向きな行動を生むこともある
最後に、もう一つ大事な気づきを。
塚本さんは「断ることは、別の形でいい関係性を継続していけるチャンス」と言っています。
僕はこれまで、「頼まれごとを断る=不義理」だと思っていました。
でも、忙しいのに無理して引き受けて中途半端になるくらいなら、最初に「今は難しいです」と正直に伝える方が、結果的に信頼を損なわないことに気づいたんです。
それは仕事でも、プライベートでも同じ。
“断ること”もまた、行動の一つなんだと、この本を読んで感じました。
この本を読んで、行動の“武器”を手に入れてほしい
塚本亮さんの『「すぐやる人」と「やれない人」の習慣』は、行動できない自分にモヤモヤしている人、何かを始めたいけど一歩が踏み出せない人にとって、まさに背中を押してくれる一冊です。
僕はこの本を読んで、「行動力は才能じゃない。環境と習慣で誰でも鍛えられる」という確信を得ました。
そして、それを実際に生活に取り入れることで、少しずつ自分の行動パターンも変わってきています。
もしあなたが「今の自分を変えたい」と思っているなら、まずはこの本を読んでみてください。
読むだけで何かが変わるわけじゃないけど、「変わるための行動」を起こす最初のきっかけにはなるはずです。
そして読んだ後は、ぜひ誰かにアウトプットしてください。
SNSでも、ブログでも、友達との会話でもいいんです。
そこからあなたの「すぐやる力」は、どんどん育っていきます。
一歩踏み出したいあなたに、この一冊を。
きっと今より“行動できる自分”に出会えるはずです。
今回はこんな感じで終わろうと思います!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇♂️
でたまた 🌱
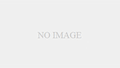

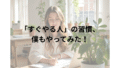

コメント